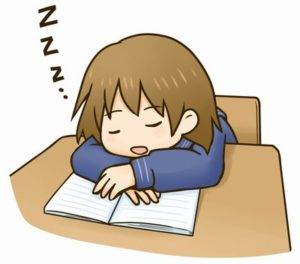子供のADHD 育児のコツ
今回はADHDのお子さんの将来を見据え、ハンデにならないよう伸び伸びと育てるコツをご紹介します。
子供のタイプ別接し方
子供のADHDには、落ち着きがなくじっとしていられない多動・衝動性優勢型と、ぼんやりして仕事がなかなか始められない不注意優先型があります。
→ADHDの3つのタイプと症状別対処法
活動的な多動・衝動性優勢型の子供は、とにかくその有り余るエネルギーを発散させる場が必要です。スポーツをさせたり、泊りがけの行事に参加させてやり過ごしましょう。
トラブルを起こして困らされることも多いでしょうが、厳しい躾や体罰は非行・反抗の元になります。子供には自己コントロールが難しいのだと理解してあげてください。
おとなしい不注意優先型の子供は、何をするにもぐずぐずして、見ている方はもどかしいかもしれませんが
親が先回りしてなんでもやってしまうと主体性が育ちません。
また無理やり塾やクラブに入れたり、活動させることは本人を苦しめるだけの結果となってしまいます。
長い目で見ながら、あせらずゆっくり見守っていきましょう。
[ad#ad]
ADHDの子育て 9つの方針
ADHDの子供にとっては、毎日が不安と緊張を感じやすく、親にとっても悩みやストレスを抱えることが多いかもしれません。
ここでは、発達障害児治療の第一人者である榊原洋一教授の著書「初めに読むADHDの本」で語られたADHDの子育て論についてまとめています。
ADHDの生きにくさを理解する
ADHDの子供を育てることは苦労の連続です。しかし、一番困っているのは本人だということも忘れないであげてください。
勝手気ままにふるまうように見えても、けして悪意があるのではなく、本人にはどうしようもない事なのです。
叱らても改善することはありません。
できない事より、できることを伸ばす
できない事ばかりに注目すると、親も子供もつらくなります。
発想を転換して良い所に注目してみましょう。
ADHDの子供には、
多動・衝動性優先型なら 元気がいい、体力がある、好奇心旺盛、発想力があるなど
不注意優先型なら 落ち着いている、穏やかで怒りにくい、空想好きなどの長所が出やすくなります。
いいところをみつけたら、大げさに褒めてあげましょう。
普通の事でも、ちゃんとできたらすぐ褒めてあげましょう。
子供の自尊心を取り戻すのに効果的です。
そして良い所を伸ばして、将来に活かせないか 早いうちから考えておくとよいでしょう。
他のきょうだいと較べない
きょうだいがいる場合、成績や性格を比べるのは良くない事です。どうしても苦手な事はあるので、責めるのは効果的ではありません。
また反対に、他のきょうだいに、不公平感をもたせないように注意します。
ADHDの子にだけ部屋を与えたり、習い事をさせたり、なんでもADHDの子を優先させたり、兄弟げんかの時に一方だけかばったり…
ということがあれば 不満がたまり、ADHDの子を助けてくれなかったり、行動療法に協力したりしてもらえないかもしれません。
身近な親戚やご近所には説明しておく
冠婚葬祭の場で走り回ったりなど、周囲の顰蹙をかうようなこともあるかもしれません。
そんなときは謝ったうえで、子供のADHDを打ち明けたほうがよいでしょう。
言い訳がましく聞こえてしまったり、理解されなかったり、親のしつけのせいにされることもあるかもしれませんが
「しつけが原因ではないこと」「子供の20人に1人と、よくあること」「注意して対処すれば、生活に支障は出ない事」をきちんと伝えます。
ただし遺伝することもある事や、薬の事まで詳しく話す必要はないでしょう。
ご近所同士で子供たちがしょっちゅう一緒に遊ぶ時も、前もって友達の親御さんには話しておくとトラブルを防ぐことができます。
不注意による事故やケガを防ぐ
ADHDの子供はとくに事故にあいやすいので、小さい頃からしっかり注意をしておく必要があります。
道路は危険だという事を認識させ、
道を歩くときはよそ見をしないで、人や車に注意しながら歩くよう言い聞かせる。
そして急に走り出さないよう徹底させます。
ふだんから子供の行動範囲を一緒に歩きながら、どんなふうに注意すればいいか教えておきましょう。
また、自転車に乗るようになってからは危険が増すので、その時にも言い聞かせます。遅刻しそうで急いでいるときは特に不注意な運転をしがちです。
しつけのやり方
いう事を聞かなかった時に、大声で怒鳴ったり厳しく叱っていると子供は徐々に自信を無くします。
子供が不適切な事をしたときは、怒る代わりに罰を与えましょう。
「〇〇をしなかったから今日はお風呂掃除がかりね。」「〇〇ちゃったからテレビとゲーム一日禁止」などと因果関係をはっきり理解させます。
一方で、ちゃんとできたことは ささいなことでも、そのたびに褒めてあげてください。
毎日の行動表を作る
帰ったらカバンと服を決まったところに置く→宿題をする→明日の準備をする→遊びに行く
など おおまかな行動表を作って毎日の習慣にしてしまえば、年齢が上がるにつれて自発的にやれるようになってきます。
朝は、薬を飲んだか、歯磨きはしたかなどのチェックリストをつくれば忘れ物を減らすことができます。
勉強に集中しやすい部屋づくり
ADHDはとても気が散りやすいので、勉強机には余計なものを置かないようにして、すっきりした作業スペースをつくります。
タイマーやスケジュール表が手近にあるとはかどります。
おもちゃや本やゲームは別の部屋に置くか、視界に入らないようにし、テレビの音はなるべく聴こえないようにします。
参考⇒ADHDでも受験はバッチリ!やる気勉強法。
得意なものを見つける
ADHDの子供は他の子と自分を比べては、コンプレックスを抱きがちです。
しかし打ち込めるものがあれば、自信をつもって進むことができます。
いろいろなことに興味が移って飽きっぽいという性質はありますが、やってみて、もしそのまま続きそうなものがあれば、その時はぜひ応援してあげてください。
ADHDには苦手な仕事が多く、他の人と同じようにこなせる職業は限られますので、自分の向いていることを早めにみつけて進路を決めることが大切です。
本人が望むならアルバイト、ボランティア活動などさまざまな体験をさせてやり、将来の道を探させてあげましょう。
むやみに行動を制限したり、過保護になりすぎるのは本人の為になりません。
参考⇒ADHDに向いてるバイト(仕事)と、絶対してはいけないバイト
ADHDの子供を伸ばして育てる5つのポイント
子供は大人よりも活動的で、一緒にいるといつも振り回されてしまいます。ましてやADHD子供の子育ては試練の連続。
ここでは、ADHD研究の第一人者ラッセル・バークレー博士の著書「バークレー先生のADHDのすべて」から、ADHDの子供が自信をもって笑顔で育って行くために、子育てで気を付けたい5つのポイントを解説します。

すぐに褒める
ADHDはその場その時に意識が向くので、後で褒めたり叱ったりするのでは効果が落ちてしまいます。
他の子供の場合よりも早く、気づいたら即座に褒める、逆に良くない事をしたらその場で注意してください
またやる気と集中が続かず、遠くの報酬よりも目の前にぶら下がったニンジンに飛びついてしまうので
なにか作業をやらせる場合は飽きないように、頻繁にご褒美をあげる必要があります。
自分を好きになってもらう
ADHDの子供は一生懸命やっているのにできなくて、自信をがなくなってしまうことが多いです。
それだけでなく先生に叱られたり、まわりから「変な奴だ」と言われることもあります。
非行や反抗性障害に陥らないため、また将来を前向きに生きていくためにも、親が共感し励まし、褒めてあげてお子さんの自己肯定感(セルフイメージ)を高めてあげることが大切です。
協力して解決する
お子さんを注意するときに、アレしなさい、これしちゃだめでしょう。というだけでなく
どうしてできなかったんだろう?
どうしてやっちゃったんだろう?
どうすればできるようになるかな?
と、お子さんの話を聞きながら、いっしょに考えてみてください。
そうすることで強い信頼関係を築くことができ、解決案を受け入れてくれるでしょう。
大切なものに目を向ける
ADHDのお子さんを持つと、毎日毎日、注意しなければいけないことばかりでしょう。
でも怒ってばかりではお子さんと良い関係を気づくことが難しくなってしまいます。
そこで、本当に優先度の高いことは何か、を考えておかなければいけません。
例えば朝、自分で完璧に準備して学校に遅れないことよりも、親の愛情に包まれ穏やかな気持ちで家を出ることのほうが大事ですね。
部屋を散らかさずにちゃんと片づけること、お稽古ごとに通う事よりも、、
子供が自信をもち、笑顔で過ごせることが大事ですね。
あなたはお子さんに、どのように育ってほしいですか?
許しを与える
お子さんを寝かせた後か、自分が寝る前に、一日の事を振り返ります。いう事を聞いてくれないお子さんの行動に怒りやストレスを感じたかもしれません。しかし、それはお子さん自身にもコントロールできない事なのです。
もちろん叱らなけばいけない場面もあるかもしれませんが、厳しい態度はとらず、今日の出来事は許してあげましょう。
そして第二に、周囲の人間を許そうとしてみます。
お子さんの障害に理解のない方は、冷たい態度をとったり、時には「親がしっかりしていないから」という言葉を浴びせてきます。
でもそれは、あなたよりずっと知識がないからなのです。他人がお子さんの事をどう考えようと、あなたはお子さんを護ることに専念しなければいけません。
今日感じた怒りも悲しさも忘れてしまいましょう。
最後に、自分がお子さんへの態度を間違ってしまっても、自分を許してあげます。
お子さんの障害はあなたのせいではないし、子育てはいつも手さぐりで、何が正解かは誰にもわかりません。
その日のふるまいはどうだったか思い出し、改善できるところはあるか、それだけを考えるべきです。
女の子のADHDをサポートするには【育児】
ADHDは男女同じくらいの割合で現れますが、その表れ方には差があります。女の子のADHDは気付かれないことが多く、思春期に入ってからは正体のわからない生きづらさを抱えて苦しんでいることがあります。
そんな女の子のADHDを理解し、サポートしてあげるのは保護者にしかできない事です
女の子のADHDは、わかりにくい
男の子のADHDには多動・衝動性優先型が多く、問題行動を起こしすぐにADHDだとわかる場合が多いのですが
一方で、女の子の場合は、ボーっとしていて大人しいのでなかなかADHDだと気づかれず、生きづらさを抱えたまま大人になってしまうケースも少なくありません。
そうならないためにも、お子さんをよく観察して、ADHDの兆候があれば早めに診断と治療をうける必要があります。
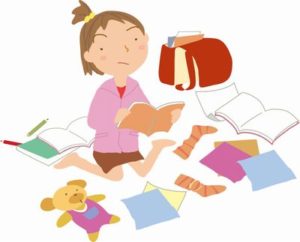
幼稚園まででは
・できること、できないことに極端な差がある
・落ち着きがない
・興味がくるくる変わる
といった特徴が現れることが多くなります。
小学校低学年では
・話を聞くのが苦手
・忘れ物が多い
・飽きっぽい
・宿題などのやる気が起きない
さらに高学年になると
・おしゃべりが止まらない
・部屋や机の上が片づけられない
・おねしょが治らなかったり、運動が苦手だったりと不器用な面がある
・ネットやゲームをいつまでも続けてしまう
といった困りごとが現れ始めます。
このことで、勉強に遅れが出たり 周りから疎外されて辛い思いをするようであれば、発達障碍者支援センターに相談して診断と支援を受けましょう。
特徴と対策
思春期(12歳ごろから)の女の子には、このような悩みが現れ始めます。
・授業に集中できず、忘れ物やケアレスミスも多い
先生の話を最後まで集中して聞くのが苦手で、ボーッとしてしまいます。
また忘れ物が多く、宿題などの用事も忘れ、プリントなどものをよく失くします。
→持ち物チェックリストなどを作ってサポートしてあげます。
またADHDの女の子は 一生懸命やろうとしても上手くいかないと、自己評価が低くなり無力感を抱いてしまいます。
失敗を叱るよりも、当たり前のことであってもできたことを褒めてあげましょう。
・時間にルーズ
計画性がなく、好きなことをやってギリギリに家を出ます。
計画を立てられないばかりか、あれもこれもと用事をつめこみすぎてパンクしてしまう。そのくせ何事も取り掛かるのが遅い傾向があります。
→おおまかな日課、行動表を決めて、生活のリズムを作ってあげましょう。
あれもこれもと取り掛からず、一つずつ確実に片づけていくように教え、見ていてあげます。
大事な用事に遅れそうなときは、急かしてちゃんと教えてあげなければいけません
・コミュニケーションが苦手で、同性に嫌われやすい
余計な事をしゃべったり、仕切りたがりなどで嫌われ、グループに入れないことがあります。
これについては次の項で説明します。
コミュニケーションが苦手
ADHDの女の子はコミュニケーションが苦手な部分があり、周りから嫌われてしまったり、上手くなじめないこともあります。

具体的には、
・気配りができない
ADHDは注意力が散漫なため、人が困っているサインを見落としたりと、細かい気配りをすることが苦手です。
人の話に割りこんだり、話題が別の事に移っても気付かず発言することもあります。
またどんな場面でもおしゃべりなため、配慮に欠けると思われることがあります。
・約束を守れない
ADHDの衝動性のため、人の秘密をポロッとしゃべってしまったり、約束より自分のことを優先してしまう事があります。
また計画性のなさから、待ち合わせに遅刻してしまうこともあるでしょう。
こういったことから、悪意があると誤解されたり 人を怒らせてしまうことも多いのです。
ですが、無理に友達を作らせようとすれば、本人の負担になってしまいます。
お子さんが人とは違う事を受け入れ、本人のペースで人付き合いを学んでいけるように見守ってあげてください。
恋愛傾向
女の子は誰しも、自分の持っていないものを持っている男の子に惹かれてしまいがちです。
何度も失敗を繰り返して劣等感を持っている女の子は、
自分の意見をはっきり主張したり、人を引っ張っていく少し強引な男子がかっこよく見えてしまいます。
ですが、そんな男の子に乱暴な扱いをされたり、言いなりになってしまうことも多いのです。
そしてすぐに別れても、また同じような男の子を好きになってしまいます。
こんなことを繰り返せば、周囲からの目も厳しいものになっていくでしょう。そうならないためにも、親御さんが、恋愛の事でも何でも相談できる理解者になってあげることが必要です。
将来、仕事についたときも、学校の勉強や友達づきあいとは違った失敗を重ね、心を病んでしまうこともあります。
きちんと能力を生かせる自分に合った職場を探すことが大事です。
参考:ADHDに向いてるバイト(仕事)と、絶対してはいけないバイト
こちらも読まれています
→サイトマップ(全記事一覧)